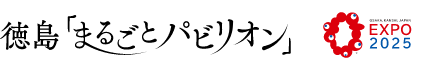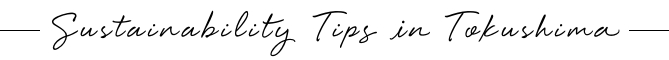〔 夢見る 〕
〔 夢見る 〕
鳴門の
ニュークラシック
ときには海上交差点として、ときには四国の玄関口として
人やモノが行き交うことで、しなやかに変化してきた鳴門。
海辺のまちに息づく、古くて新しいデザインを探しに。
photo_Shintaro Miyawaki
text_Yu Ikeo
近代建築が映す町の未来
鳴門市内を流れる撫養川(むやがわ)沿いに、ひときわ目を引くコンクリートの塊がある。戦後の建築家・増田友也が設計した〈文化会館〉と〈健康福祉交流センター〉だ。彼による近代建築が、鳴門には18棟も残っている。
低いひさしをくぐって健康福祉交流センターへ入ると視界が開けた。1階の階段下のスペースでは青い窓ガラスが、上階では4色の窓ガラスが廊下にカラフルな影を落としている。階段室では、天井に設けられた丸い窓が不思議な存在感を放っていた。

左/建築家・増田友也が設計した〈健康福祉交流センター〉。目地の幅や溝の深さに細かな変化をつけることで、絶妙な陰影が生まれている。右/健康福祉交流センター(1977年竣工)の階段室のトップライト。
「彼の建築からは自然光へのこだわりが強く感じられます」と建築家・福田頼人さんが教えてくれる。彼は〈くすの木建築研究所〉を鳴門に構えながら、増田建築の魅力を伝える見学会や講演会をたびたび開いている。

左/撫養川越しに眺める健康福祉交流センター(右)と〈文化会館〉(1982年竣工 / 左)。右/〈文化会館〉背の高い人なら手の届きそうなほど低いエントランスが、中に入ったときの広がりを演出する。
高度経済成長期、人口が増え、町全体が活気に沸いた時代。当時の鳴門の人びとは、こうした公共施設を前に町の未来を夢見たはずだ。
鳴門市文化会館
鳴門市撫養町南浜字東浜24-7
(現在休館中)
ご近所の“ドイツさん”
鳴門で少し意外なのがドイツとのつながりだ。第一次世界大戦の後、この町には約1000人のドイツ兵捕虜(ほりょ)が暮らす〈板東俘虜(ばんどうふりょ)収容所 〉が存在した。暗澹(あんたん)たる気持ちにもなるが、ここは珍しい開放的な収容所で、彼らは意外にも文化的な生活を送り、地域の人とも積極的に交流したという。なかでも熱心に取り組まれたのが音楽活動だ。地域の人を招待し100回を超える演奏会を開いた。当時、ベートーヴェンの交響曲第9番がアジアで初めて全楽演奏されたのは有名だ。地域の人も彼らを「ドイツさん」と呼び、進んだ技術や文化を採り入れていった。
鳴門駅近くにある〈ドイツ軒〉では、その歴史を窺い知れる。初代店主が捕虜になったパン職人のもとで修業を積んだのがきっかけで、1919年に徳島市で創業。その鳴門支店として1937年に開業したのがここだ。その製法を受け継いで、現在は3代目の岡則充(つねみつ)さんがパンを焼く。ドイツパンはもちろん、戦前からつくっているという甘い菓子パンも変わらない人気メニューだ。

左/レンガ調の店構え。右/食パンにりんごジャムや白あん、バタークリームなど6種を塗り挟んだ「食パンサンド」は常連さんに人気。
現在進行形のかたち
地形的な理由から、常に外からの影響を受けてきた鳴門。この町のものづくりにも、それは表れている。まずは鳴門の焼き物、大谷焼。江戸後期にお遍路旅にやってきた大分の焼き物師が大谷村を訪れ、この地の土をロクロで成形し焼き上げたことがその始まりだ。現在6軒の窯元があるが、〈森陶器〉では、かねてより藍甕(あいがめ・藍染め用の甕)や睡蓮鉢などの大物を焼いてきた産地特有の大きな登り窯が一般開放されている。
「平地に築き上げたものでは日本最大級の登り窯です」と5代目の森崇史さんが案内してくれた。昭和後期の閉窯からずいぶん経つが、付着した薪の灰が高温で溶けガラス質になった壁が、その歴史を伝えている。

左/ロクロで成形する大谷焼の職人。右/森崇史さんの器。右の器の赤茶色の縁部分が、大谷焼の原土の色。藍染めの染料づくりにつかわれた灰を釉薬(ゆうやく)に調合するという昔ながらの手法を用いている。
鳴門には木工の町の一面もある。明治期、それまで盛んだった造船業が衰退すると、多数の船大工が家具職人へと転身し、戦後は木工業が発展した。そんななか、国内外にファンを増やすのが〈宮崎椅子製作所〉だ。

左/無数の部品のなかから適切なパーツを選び、組み立て作業を行う職人。パーツのカットは機械で自動化されているが、パーツのヤスリがけや組み立て、イスに仕立てるファブリックの縫製などはすべて人の手で行う。現在スタッフは30人ほど。右/〈宮崎椅子製作所〉が復刻した、カイ・クリスチャンセン氏による名作イス「No.42」。独特のハーフアームや可動式の背もたれなど細かな工夫が。
昭和の創業より鏡台のイスを下請けで製造してきたが、需要は減少。その技術力を活かし2000年に始めたのが、国内外の外部デザイナーとのコラボレーションでつくるイスの自社ブランドだ。アイテム数は現在80を超え、その売り上げの4割が海外の卸先。なかでもデンマークのデザイナー、カイ・クリスチャンセン氏による名作「No.42」においては、復刻製造できる工場は世界でもここだけなのだとか。
うねりがつくり出す風景
カーナビに従って到着した先は、畑の広がる長閑(のどか)なエリアでは、少し目立つ一角だった。「おーい、こっち!」と初対面とは思えないフランクさで迎えてくれたのは山口輝陽志(きよし)さん。もともと水着を製造していた父親の縫製工場を継ぎ、15年前にサーフィン用ショーツブランド〈ナルトトランクス〉を始めた。2019年には道路向かいに企業型保育園〈ナルトキッズ保育園〉を、2021年にはショップ兼ギャラリー〈モッコクハウス〉をオープンし、衣服だけでなく地域のコミュニティづくりにも力を入れている。

左/〈ナルトトランクス〉の工房にある糸棚。引き出しを開くと、同色の糸が入っている。右/ランニングやヨガなど日常のあらゆるシーンにはける「every day,every one」シリーズ。リサイクル再生ポリエステルの糸から開発した生地は、速乾性抜群。
鳴門で生まれ育ち、サーフィンと西海岸カルチャーを愛する山口さん。20代は高松での社会人生活を満喫していたが、気づけば家に帰るようにここに戻ってきていた、と笑う。
よく見ると、ブランド名のロゴは「Naruto」ではなく「Naluto」になっている。
「Naluはハワイの言葉で『うねり』という意味です。この場所でやっていくと決めたときに名づけたんですが、ピッタリでしょう?」
いつの時代も、内なるものが外からの風と混ざり合い、カルチャーが生まれてきた鳴門。人びとは水平線の向こうに夢を見て、新しいものをたくましくも柔軟に受け容れてきた。この町の風景がいつも新鮮な驚きに満ちているのは、土地と人が響き合うように“うねり”を生んだ、軌跡がそこにあるからだ。

鳴門市の内湾にあるウチノ海。湖のように静かな内海に、釣り屋形(釣り人のためのイカダ)がたくさん浮かぶ。中央のハート形の島は鏡島と呼ばれる無人島。
「FRaU S-TRIP 2023年4月号 もっともっと
サステナブルな『徳島』へ」講談社刊より