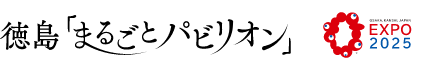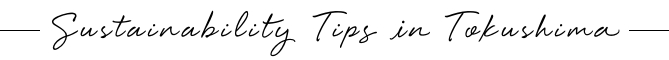〔 生み出す 〕
〔 生み出す 〕
奇跡の川の
ものづくり
四国中央部の水源から四国山地を横断し、徳島を西から東へ流れる吉野川。
日本有数の大河川として水運技術が発展し、
流域ではさまざまなものづくりが生まれた。
吉野川河口から上流の美馬市脇町まで。
現代のつくり手に会いに、奇跡の川をたどる。
photo_Shumpei Ohsugi text_Yu Ikeo
井上味噌醤油
麹菌のご機嫌をとったり職人さんによい仕事をしてもらったり
味噌の環境づくりが僕の仕事です
鳴門市撫養町岡崎字二等道路西113

左/麹菌が活発になる温度と湿度に保った麹室で行われる、手入れの作業。米麹の発熱で 米の中はじんわり心地よい温かさ。右/杉樽の中で、茹でた大豆と米麹を混ぜ合わせる井上さん。この仕込みから1年の四季をへて味噌が完成する。
風土そのものが味
旅の始まりは、吉野川が紀伊水道へ流れ込む岡崎港。内海のすぐそばに、〈井上味噌醤油〉はある。創業1875年。150年近く変わらない手仕事による味噌づくりで、フランスのシェフも愛用する生味噌があると聞いてきた。7代目になる井上雅史さんは「ここには味噌づくりに必要な大豆、塩、米が揃う環境があります」と言う。吉野川流域では藍の染料になる蓼藍(たであい)栽培が有名だが、その間作として栽培されたのが阿波白目大豆(あわしろめだいず)だった。加えて鳴門は塩づくりが盛んで、徳島平野の米もあり、当然水も豊富。
味噌づくりの根幹となる麹室での「手入れ」作業を見せてもらった。もろぶたという木箱をつかって麹菌を40時間かけて生育させるのだが、成長を促すために適宜混ぜる。手で麹菌の「息吹を感じ」ながら、麹菌の成長具合で混ぜ方や回数を変えるというから、微細な感覚が必要だ。麹菌が十分な酵素をつくったら塩を加えて生育を停止。これと茹でた大豆を木樽に入れ、 年をへて味噌になる。

左/150年近く現役のものもある木樽。修繕をしながら200年つかい続けるために、すべて竹タガで締める。右/木樽で5年以上天然醸造し、完熟した味噌「御膳ねさし」。コクが強く、ソースやタレの隠し味にもなる。
天然醸造を追求する井上さんだが、「僕の仕事は味噌の環境づくりでしかないんです」と軽やか。いただいた味噌は、風土の味そのものだった。
森工芸
「どんな模様になるんかな?」が創作の源
徳島市末広3-5-34

左/天然木を薄くスライスしたツキ板でトレイを制作する〈森工芸〉の森寛之さん。連続した木目の組み合わせと配置が、見たことのない模様を生む。右/森さんのアトリエ。制作のきっかけになったスピーカーやトレイなど、さまざまな試作品が積み上げられ、レコード棚を彩る。
新しい景色が見たいから
末広にある〈森工芸〉を訪れると、工場片隅の秘密基地のような一角で、森さんが黙々と手を動かしていた。
吉野川河口部、デルタ地帯の徳島市末広は、まわりを吉野川水系の支川に囲まれている。かつては、内陸の林業地帯からイカダで運ばれてきた木材が集まる貯木場も多くあり、明治期まで盛んだった造船業の衰退後は、家具などの木工技術が発展してきた。そんな木工の町で、森工芸は70年以上ツキ板を製造してきた。ツキ板は天然木を薄くスライスしたもので、建材や家具などの合板に貼りつけてつかわれる。その技術を活用し、オリジナルブランド「POKE」の名で現代生活に合ったものづくりに挑戦しているのが3代目の森寛之さん。数年前、音楽好きが高じて自作したスピーカーにツキ板を貼ってみたのがきっかけで、模様の虜になったという。

左/紙束のようにパラパラめくれるツキ板。厚さはなんと0.2mm。右/ツキ板を何枚も重ねて貼り合わせた材をくり抜いてつくった器。繊細でカラフルな縞模様はどれも唯一無二のもの。
「組み合わせで、思いもよらない模様ができる。その新しい景色を見たくて、つくらずにはいられなくなる。つくったものが溜まるんで、売らないといけなくなるんです(笑)」
自分を「ただの木目好き」と謙遜する森さん。色とりどりのトレイには、彼の好奇心がそのまま宿っている。
岡田製糖所
秘伝の製法などはありません。うちは地域の農家ですから
板野郡上板町泉谷字原中筋12-1
地域史とともにある甘み
徳島と香川の県境に広がる阿讃山脈の裾野に〈岡田製糖所〉はある。阿波和三盆糖と呼ばれる独自の砂糖が200年以上つくられてきたこの地で、いまも昔ながらの手作業でつくっているのがこちら。代表の岡田和廣さんが、背後の山から吉野川の方向までを指して言う。
「このあたりは扇状地で比較的痩せた土地ですが、水はけがよく、南向きで日当たりがよい。蜜の詰まった竹糖ができるんです」

左/阿波和三盆糖のみでつくられた落らく雁がんなどの干菓子。右上/サトウキビの搾り汁を煮詰める工程。このあと自然冷却すると、半固形状の砂糖の塊ができる。右下/沖縄のサトウキビに比べて細く短い竹糖。糖度が上がる12〜2月上旬に収穫し、新鮮なうちに加工する。
敷地には近隣の農家で収穫された在来のサトウキビ「竹糖」が山積みになっている。これを圧搾しながら搾汁し、アク抜きしながら煮詰めると、茶色の砂糖の塊ができる。
ここから糖蜜を抜いて砂糖を白くするために、職人が両手のひらで「研ぐ」のが和三盆の特徴だ。これを一日1回行い、ひと晩重石をかけ、を5日間続ける。一般的な白砂糖では機械にかけて糖蜜分を精製するのに対して、ここでは研ぎというある意味“不完全な”精製をすることで、サトウキビの風味をたっぷり残した砂糖になるのだ。できたての和三盆をいただくと、こっくりとした甘みが舌の上でほどけていく。
この地の日常として、自然のまま、ありのままにつづく味。しみじみ味わいたくなる甘みの理由が、その言葉に込められていた。
Awagami Factory
阿波和紙の産地でありつづけるためにどんな依頼にも
「できます」と応えてきました

左/楮。和紙には内側のやわらかい皮の繊維をつかう。右/2022年に誕生した和紙「紙麻」をチェックする中島さん。楮に加え、繊維が太くて長い麻をたっぷり漉き込んでいるため強度がある。強く引っ張っても布のように伸びて、ちぎれない。
世界とともに進化する和紙
阿波和紙伝統産業会館という名前からは意外なほどに、内部は自然光に満ち明るい雰囲気。ここでは〈Awagami Factory〉ブランドの阿波和紙の製造工程を見学できる。
和紙の原料は主に、楮(こうぞ)、三椏(みつまた)、雁皮(がんぴ)。繊維を取り出し、分解し、漉(す)いて乾かすことで完成する。Awagami Factoryの母体、富士製紙企業組合の工場長・中島茂之さんが言う。
「楮と三椏は肥沃な土壌の四国山脈周辺で栽培しやすく、雁皮の栽培は阿讃山脈の砂地に適しています。そして、吉野川の水。これらがすべて揃ったこの土地で、和紙づくりが行われてきたのは自然なことです」

左/手漉きで和紙を漉く職人。右/和紙の藍染めも行っている。
阿波和紙の歴史は古く、いまから1300年前に阿波忌部氏(あわいんべし)がこの地方に和紙づくりを伝えたという。明治の最盛期には吉野川流域に500軒超の紙漉き工場が点在。それが、現在はここ1軒に。「産地として存続するために、どんな依頼にもまずは『できます』と応えてきたんです」と中島さんは軽やかに微笑むが、そこには大変な努力が必要だったはず。製造の工夫や和紙の啓蒙活動が実を結び、いまや60ヵ国超の取引先をもつまでになった。写真プリントや美術作品の修復用など、主にアート業界の依頼が世界中から舞い込む。
伝統は時代のニーズに応じて変化してこそ、未来につづく。そのことを一枚の和紙が物語っている。
世界への扉としての川
旅の最終地点は、「うだつの町並み」で有名な美馬市脇町。「ここは、船乗りさんが風待ちをした町でもあります」
案内してくれたアウトドアガイドの牛尾愛子さんが指差す先には、〈オデオン座〉と描かれた西洋モダンな建物。鉄道が通る明治期まで、物流の主役は吉野川の帆船だった。海風をつかって川を上る帆船は、風がなければ動けない。何日も風を待つ船乗りが劇場や飲み屋に集まり賑わった時代を、その建物は伝えていた。
都への供給源として、ものづくりが発展した吉野川流域。川は創造の源であり世界への扉でもあったのだ。

左/明治期の吉野川、池田-徳島市間で活躍した帆船「平田船」の模型。〈阿波池田うだつの家・たばこ資料館〉にて。右/1934年に芝居小屋として建てられ、いまも営業をする〈脇町劇場オデオン座〉。かつては吉野川流域の各町に同様の劇場があったが、現存するのはここのみ。
「FRaU S-TRIP 2023年4月号 もっともっと
サステナブルな『徳島』へ」講談社刊より